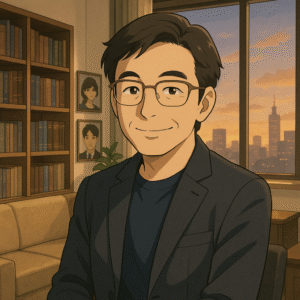●「不便だったけど、楽しかった昭和。あの心のままに、今の時代を遊びつくすブログです」
●シニアの新しい挑戦をご一緒に!共に助け合い楽しむセカンドライフを過ごしませんか!
こんにちは、グランパです!
1961年生まれの64歳、『わくわく昭和セカンドライフ』を運営しています。
ビートルズに憧れた少年時代、バブルに踊った青年期、そして仕事一筋だったサラリーマン生活。同じ時代を歩んできた皆さんなら、懐かしく思い出される日々ではないでしょうか。
セカンドライフはこれからが本番!私たちシニア世代がこれから過ごす時間を、もっと豊かに、もっと楽しく過ごすためのヒントを皆さんと一緒に探していきたいと思っています。
シニア世代のこれまでとこれから
長らく会社勤めをしてきましたが、今は『わくわく昭和セカンドライフ』と名付けたこのブログで、同世代の皆さんと経験や情報を共有する毎日です。私たちが歩んできた昭和から平成への激動の時代。その経験は何物にも代えがたい宝物だと思いませんか。
歳を重ねるごとに新しいことに挑戦するのはちょっぴり勇気がいるようになりました。でも「まだ見ぬ世界」への好奇心は衰えていません。特に最近はスマホやSNSなどデジタル技術に興味津々です。孫に教わりながら、時には先回りして驚かせることも(笑)
シニアと共に成長するブログについて
『わくわくセカンドライフ』は、私たち60代、70代のシニア世代が互いに学び合い、励まし合いながら新しいことに挑戦していく交流の場です。上手くいったこと、失敗したこと、どちらも包み隠さず共有していきます。
同じ目線で共に歩み、時には若い世代から学ぶ姿勢も大切にしています。これから新しいことにともにトライして、結果が上手くいかなくても喜び合い励まし合っていける仲間を募集中です。
シニアの日常と趣味の楽しみ方
朝のウォーキングがルーティン。季節の移り変わりを感じながら歩くのが日課です。最近はスマホで風景や草花の写真撮影にもはまっています。写真の腕前はまだまだですが、日々練習中!
シニア向けの料理も楽しみの一つ。妻に教わりながら、時には創作料理にも挑戦。「男の料理」と呼ばずに、自然体で楽しんでいます。
読書、ベランダガーデニング、そして昔から続けている将棋も大切な時間。これからは60代からの新しい趣味にも挑戦したいと考えています。
また、芸能情報発信も継続的に楽しんでいます。
シニア仲間と一緒に歩みましょう
このブログを通じて、同じ世代の皆さんと新しい発見や喜びを分かち合えたら嬉しいです。成功も失敗も笑い飛ばせる、そんな仲間と和気あいあいとセカンドライフを充実させていきましょう。
「まだ見ぬ世界」は、きっと想像以上に楽しいはず。一人では勇気が出ないことも、仲間がいれば大丈夫。私も皆さんから学ぶことがたくさんあると思います。
どうぞお気軽にコメントやメッセージをください。一緒に楽しく歳を重ねていける仲間との出会いを心から楽しみにしています。
『人生100年時代、これからが本番!共に学び、共に成長しましょう』
シニアの挑戦をサポートする今後の記事カテゴリー
- シニアのデジタルライフ – スマホやSNSの活用術
- 60代からの健康維持 – 無理なく続けられる健康法
- シニアの趣味探し – 新しい自分を発見する趣味の世界
- シニアの節約生活 – 年金生活を豊かに過ごすコツ
- 思い出の共有 – 私たちが生きてきた時代の思い出話など
- 芸能情報発信
- そのほか楽しいこと・ワクワクすること・興味津々なことetc
- 大切な読者様からのリクエスト
座右の銘:「好奇心は最高の若返り薬」
最近のチャレンジ:YouTubeでの動画編集、スマホ写真の撮影技術
これからやってみたいこと:旅行ブログ、地域の歴史探訪、簡単なプログラミング
賛同してくださる方々と和気藹々とチャレンジできたら嬉しいです。 一緒にわくわくするセカンドライフを創っていきましょう! こんな私ですが、どうぞよろしくお願いいたします。
仲間の声
「グランパさんのブログで勇気をもらい、私も70歳からスマホ写真を始めました。同じ失敗や発見があって共感しています」(72歳・田中さん)
「同世代の方がデジタルに挑戦する姿が心強いです。教え合いながら一緒に成長できる仲間ができました」(67歳・鈴木さん)
このプロフィールページは2025年5月に更新しました。今後も新しい挑戦や発見があれば随時更新していきます。
🌟「わくわく昭和セカンドライフ」は、64歳の私自身や友人、知人がこれまでの生活の中で感じたこと、試してよかったことをまとめたブログです。
ここでご紹介している内容は、あくまでも個人の体験談や実感に基づくものであり、医師や医療専門家からのアドバイスではありません。
健康や体調に不安がある場合は、必ず専門の医療機関にご相談ください。
また、ブログ内で参照した資料や出典については、記事内にリンクを掲載していますので、必要に応じて確認することができます。
それでもこのブログが、同じような悩みや関心を持つ方々にとって少しでもヒントや励みになれば幸いです。
🌟【Google向け免責事項】
本記事は、筆者や周囲の体験談をもとに執筆しています。
医療上の判断が必要な場合は、必ず専門医などの適切な医療機関にご相談ください。
なお、記事内に掲載している参照資料や出典リンクもあわせてご確認ください。